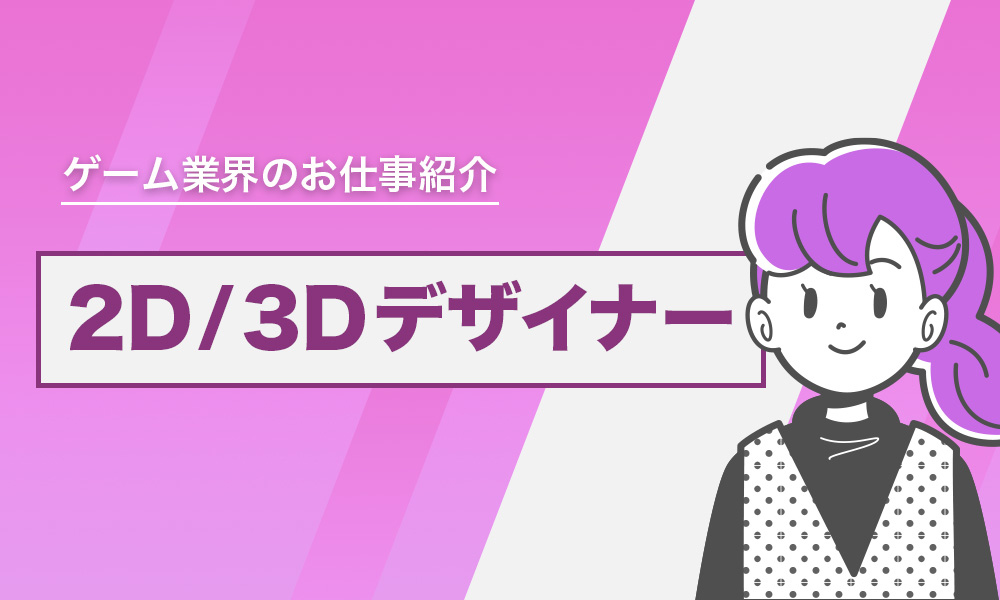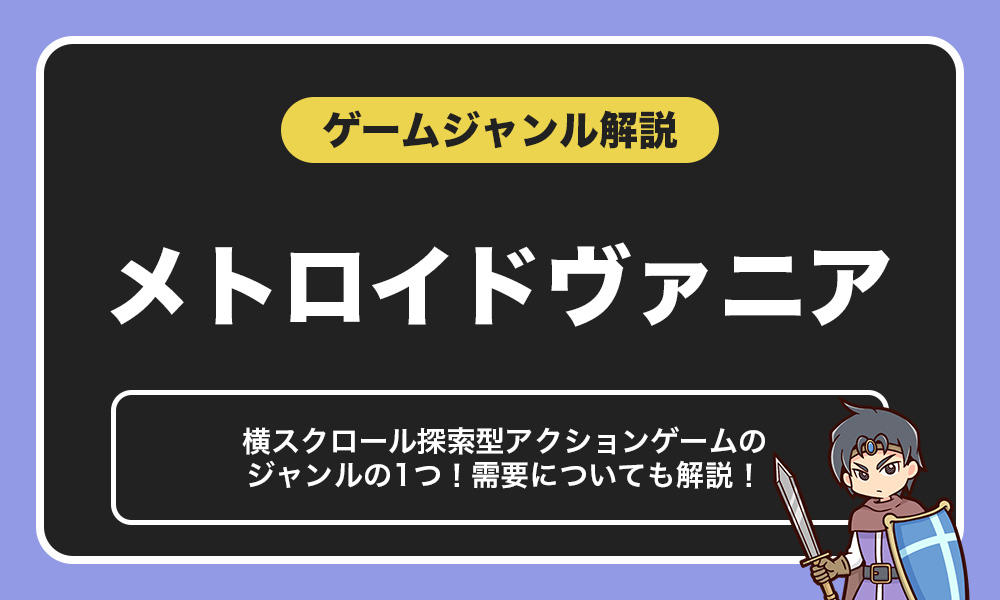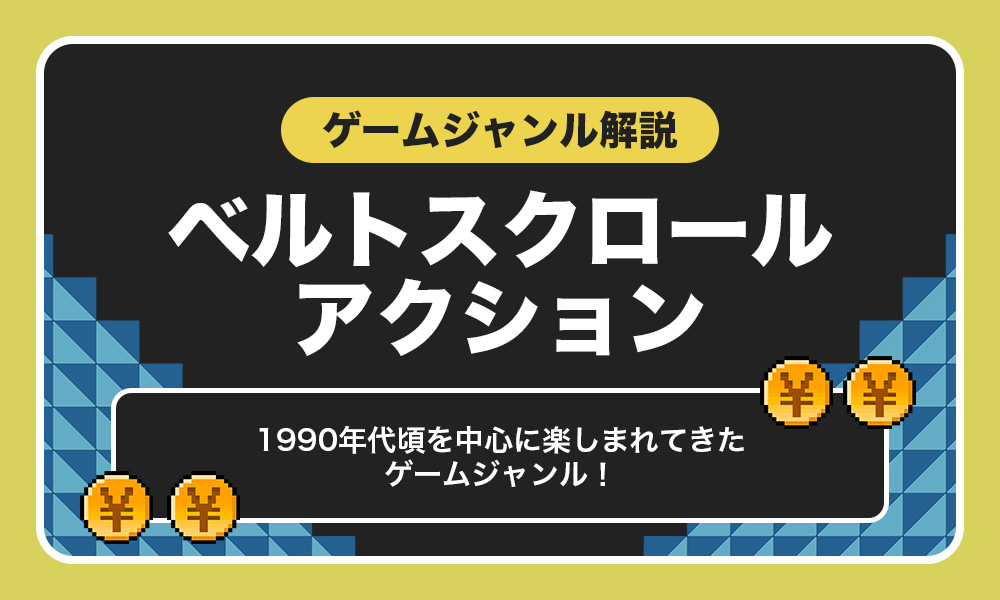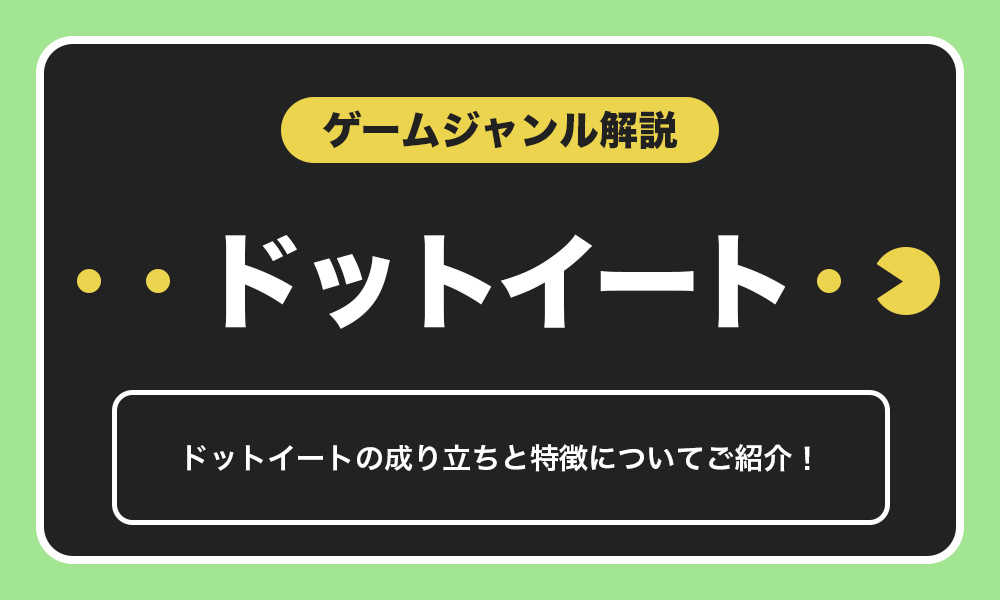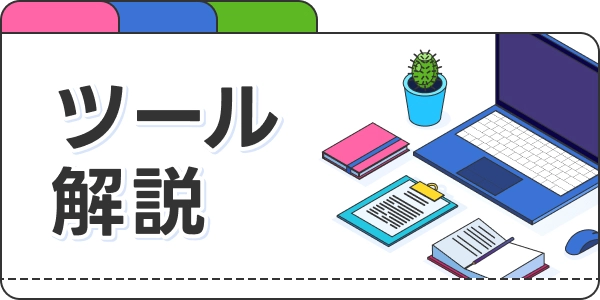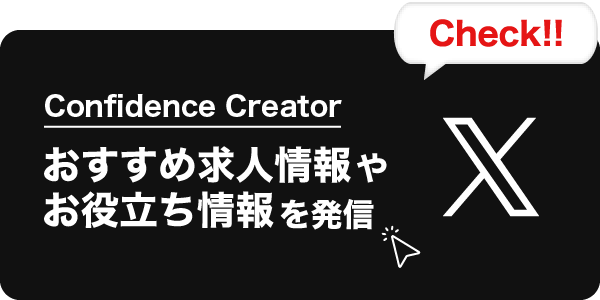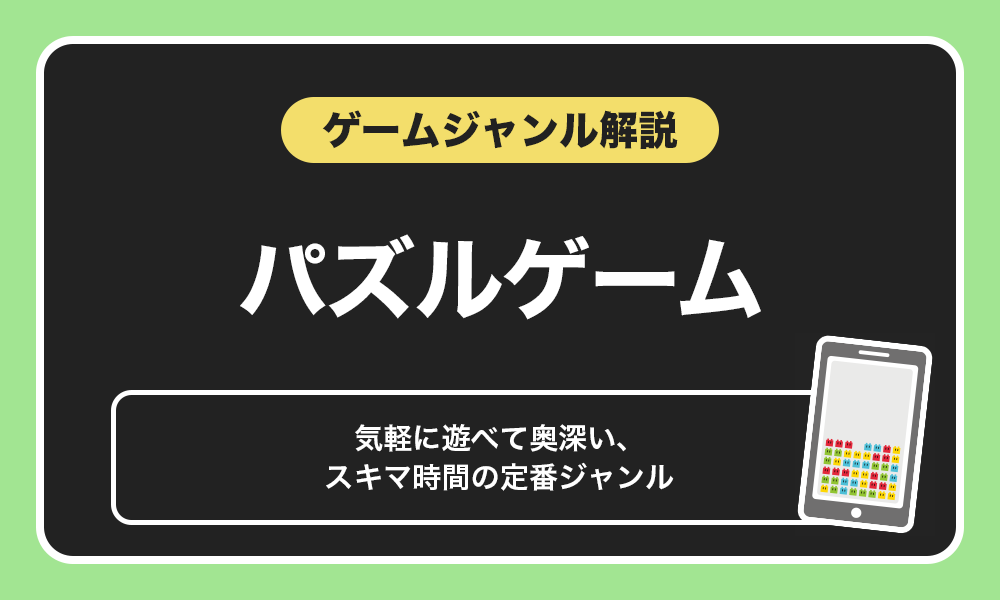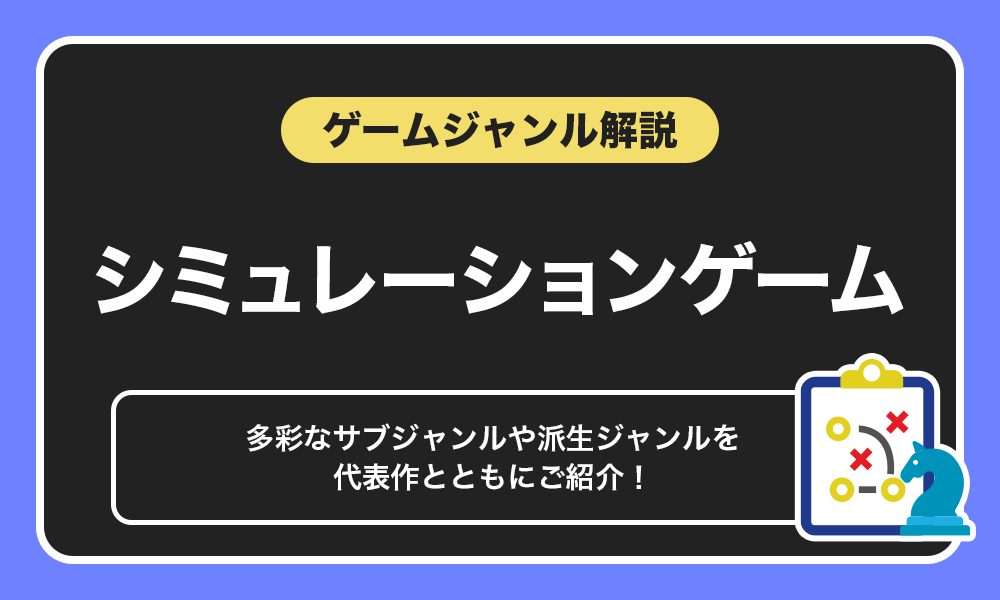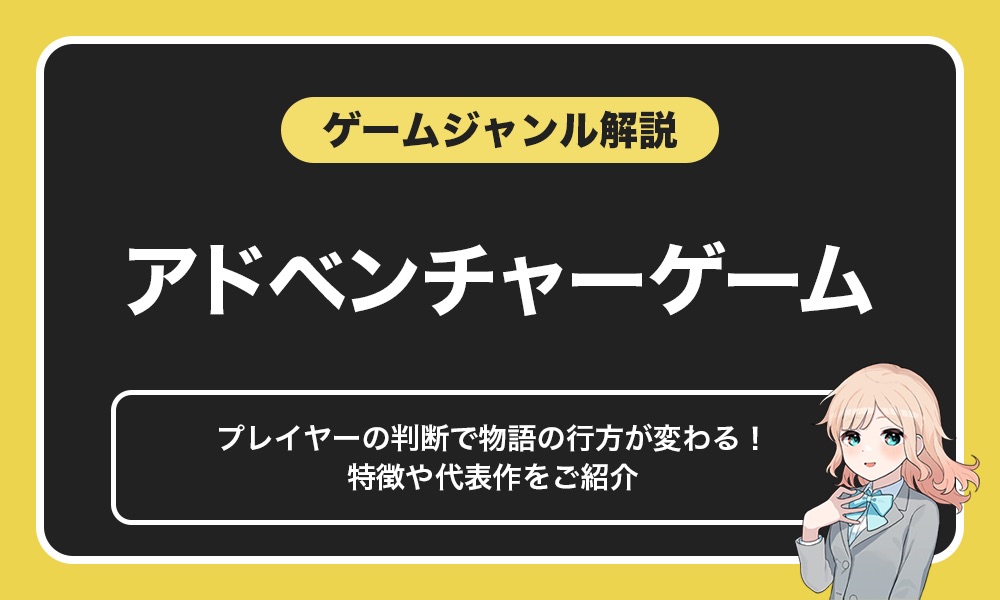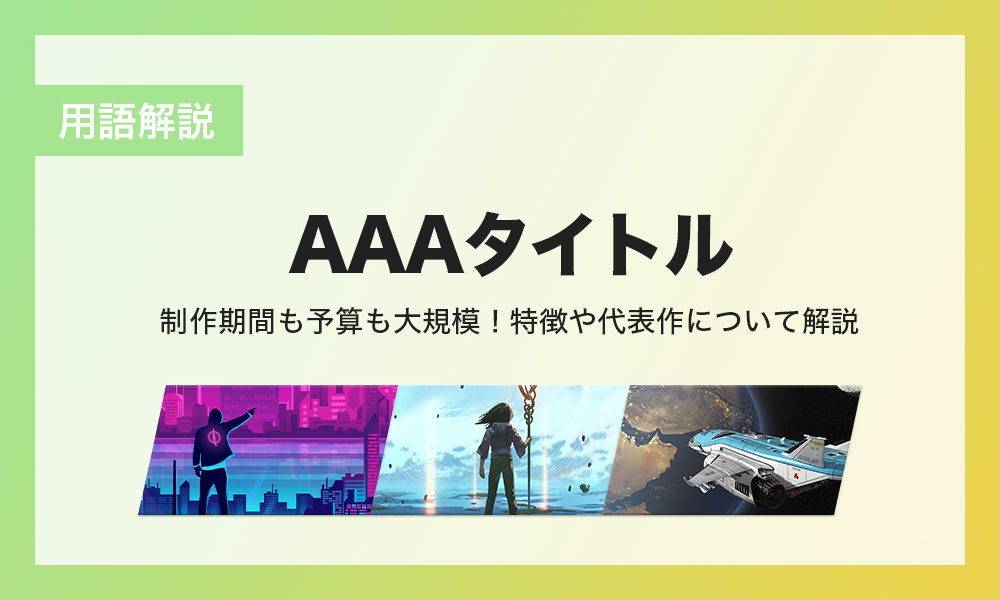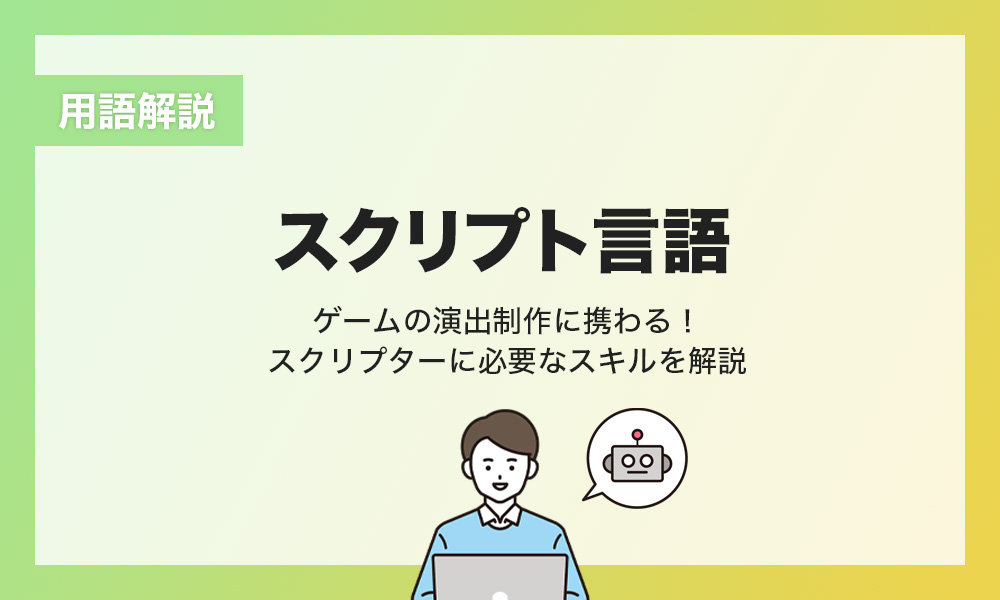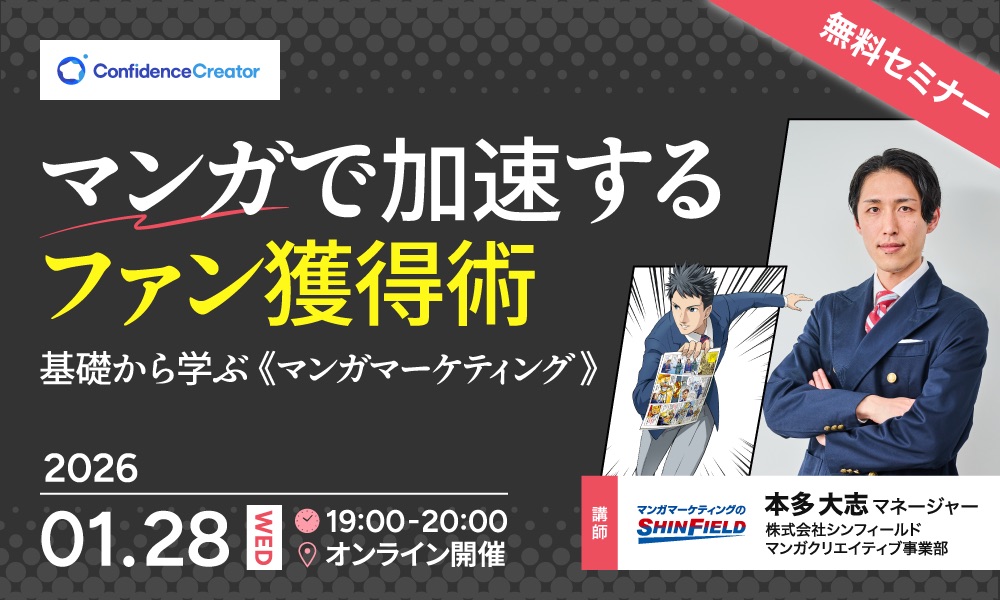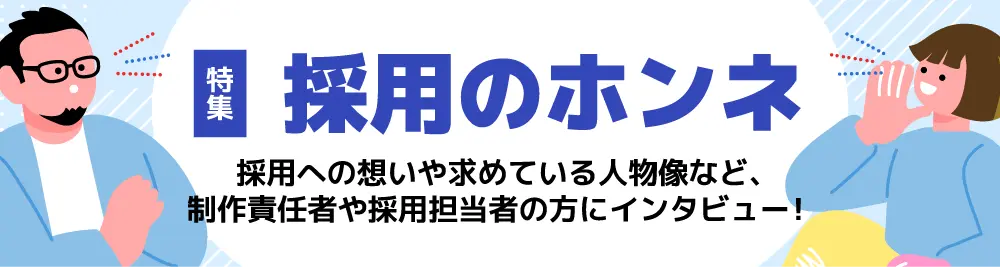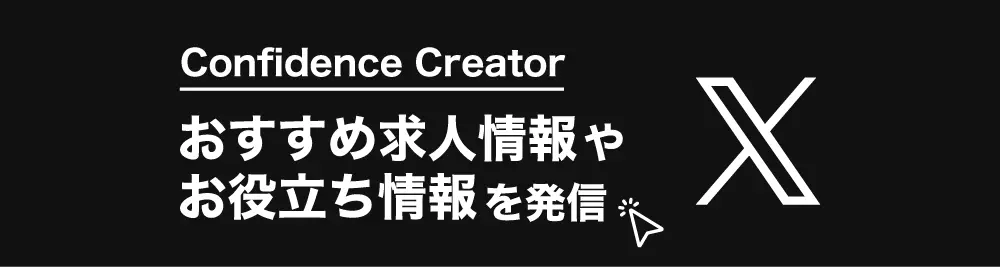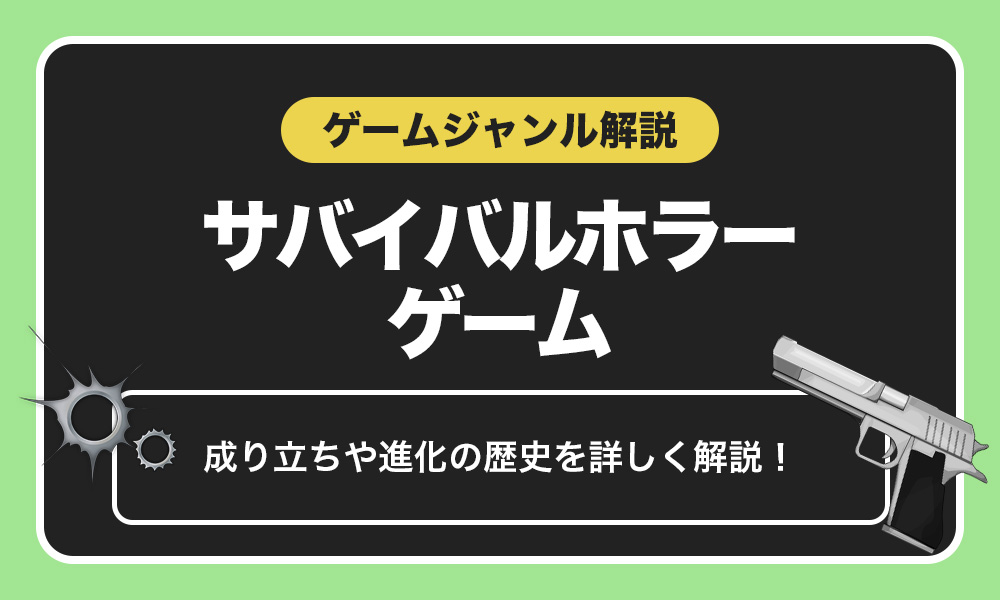
ゲームの世界には数多くのジャンルがあり、その中でも「ホラーゲーム」は根強い人気を誇るジャンルのひとつです。
今回は、ホラーゲームの中でも特に古くから存在している「サバイバルホラー」に焦点を当て、なぜ多くのプレイヤーがこの恐怖の世界に引き寄せられるのか、その成り立ちや進化の歴史を紐解きつつ見ていきたいと思います。
サバイバルホラーゲームとは?
まず押さえておきたいのは、「ホラーゲーム」という言葉はゲームのシステムを指すものではなく「恐怖を題材にしたゲーム作品」の総称である、ということです。アクションでもアドベンチャーでもパズルでも、「怖い」ことを主軸にしていれば、それはホラーゲームになります。つまり「ホラーゲーム」とは、RPGやシューティングといった、操作や進行のルールに由来するジャンル名ではなく、"テーマ性"に根ざした名称なのです。
ホラーゲームの魅力とは
それでは、ホラーゲームの特徴を理解するために、他の恐怖系の娯楽との違いを見ていきましょう。
たとえば、絶叫マシンやお化け屋敷のようなアトラクションでは、スピード感や音、暗闇などによる身体的なスリルが中心で、自分で展開を変えることはできません。いわば受け身の恐怖体験が中心で、短時間で強い恐怖刺激を受け、体験後には大声で笑ってしまうような爽快感や解放感を得られるのが特徴です。一方、ホラー映画や小説は心理的な恐怖を描く点に優れています。観客や読者は、映像や文章を通して「安全な場所から恐怖を観察する」という立場でスリルを楽しみます。
ホラーゲームは、これらの要素を取り込みながらも、プレイヤー自身が「当事者としてその場にいるように恐怖を体験する」という点が大きく異なります。操作や選択がプレイヤー自身の手に委ねられているため、逃げる・隠れる・立ち向かうなどの行動にリアルな緊張感が伴いますし、その行動は展開にも影響します。このインタラクティブ性によって得られる強い没入感こそが、ホラー×ゲームの掛け算で生まれる、ホラーゲーム独自の恐怖体験であり、最大の魅力と言えるでしょう。
サバイバルホラーゲームの特徴
さて、そんなホラーゲームの中でも、特に“生き残ること”に重きを置いているのが「サバイバルホラー」というジャンルです。
舞台は、多くの場合、閉鎖された空間や見知らぬ土地で、不気味な静寂が漂い、ゾンビや怪異といった超常的な敵が潜んでいます。また、主人公は非力な存在として描かれることが多く、頼れる武器は脆弱で、弾薬や回復アイテムも潤沢ではないので、使用には慎重な判断が求められます。加えて、謎解きや探索といった要素も多く盛り込まれており、知的な試行錯誤も必要です。
このように、サバイバルホラーは「怖さ」だけでなく、危機的状況での判断、行動、心理的プレッシャーを通して、プレイヤーに深い没入体験を提供するジャンルなのです。
サバイバルホラーゲームの歴史と派生・サブジャンル
プレイヤーに「生き延びる恐怖」を体験させるサバイバルホラー。そのリアルな緊張感は、作品ごとに独自の進化を遂げながら、多様なスタイルへと広がっていきました。ここでは、ジャンルの誕生と、その後の発展を見ていきます。
サバイバルホラーの歴史と発展
ホラー要素を持つゲームの歴史は古く、1982年に発売された『Haunted House』ではすでに、探索要素やアイテム管理など、のちのサバイバルホラーゲームにみられる特徴が備わっていました。
また、1989年に発売されたファミコンソフト『スウィートホーム』は、のちの『バイオハザード』にも影響を与えたとされる、ホラーRPGの先駆けです。さらに、3Dグラフィックスとパズル要素を組み合わせた1992年のPCゲーム『アローン・イン・ザ・ダーク』は、サバイバルホラーの雛形となりました。
そして1996年、プレイステーションに『バイオハザード』が登場し、「サバイバルホラー」という言葉を世に広めることになります。『バイオハザード』は狭い洋館での探索、限られたアイテム管理、セーブの制限、更にゾンビという脅威、と、まさに「surviveする=生き残る」ための恐怖体験を表現した、画期的なゲームでした。一方、1999年に登場した『サイレントヒル』は、より心理的な恐怖に傾倒し、プレイヤーの心にじわじわと忍び寄る不安を表現して好評を博します。
これらのタイトルは、サバイバルホラーを一大ジャンルとして確立させ、以降、多様な派生作品を生み出す土台となりました。やがて2000年代に入ると、よりスピーディーな展開を重視した「アクションホラー」や、戦闘よりも探索・謎解きに重きを置いた「脱出系ホラー」なども登場し、ホラージャンルは着実に発展を続けています。
技術と多様性の進化
現在では、PS4、PS5などのハイスペックマシンの登場によって、リアルなグラフィックや音響効果を駆使した演出が可能となり、より洗練された臨場感あふれる表現が、新しい恐怖を生み出しています。
とくにVRホラーは、プレイヤーの視界全体を支配することで、従来のゲーム以上に強烈な没入感の提供を実現しました。また、Switch、Steamなどのプラットフォームでは、個人や小規模チームによるインディーのホラー作品が数多く登場しており、90年代後半作品をオマージュしたクラシック回帰の動きも見られます。
一方、スマートフォンの普及によって、よりライトなホラー体験が可能な作品も増えてきました。脱出ゲーム系や、ホラー要素を取り入れたパズルゲーム、あるいは強制スクロール型のベルトアクションゲームなど、ジャンルの壁を超えた「ハイブリッド・ホラー」が多数登場しており、ホラー初心者でも気軽に楽しめる環境が整ってきています。
サバイバルホラーゲームの名作・有名タイトル
では、サバイバルホラーゲームを代表する名作や注目作は何でしょうか。前章でご紹介した作品を含む、4つの人気タイトルの特徴や背景をご説明していきます。
『バイオハザード』
『バイオハザード』シリーズは、サバイバルホラーというジャンルを世界的に確立させ、その後のホラーゲームに多大な影響を与えてきました。1996年の初代作では、限られた弾薬や回復アイテム、閉鎖空間での探索など、緊張感に満ちたゲーム体験を提供し、ジャンルの基本スタイルを築きました。
その後もシリーズは時代とともに視点や演出を進化させつつ、ゾンビや生物兵器との戦いを軸にした物語を重ねており、リメイクや新作も次々に登場しています。今なお全世界で高い支持を獲得し、サバイバルホラーの最前線を走り続けている不朽の名作です。
『サイレントヒル』
1999年に登場した『サイレントヒル』シリーズは、精神的恐怖を重視した独自の作風で知られます。
霧と闇に包まれた架空の町「サイレントヒル」を舞台に、罪や喪失といった人間の内面を深く描くストーリーが展開されます。また、異世界への変化を告げるサイレンや、不穏な音響演出も高く評価されました。特に『サイレントヒル2』は心理ホラーの傑作として広く認知されており、サバイバルホラー全体に強い影響を与えました。
『The Walking Dead: Saints & Sinners』
人気ドラマの世界観を基にしたVR専用のサバイバルホラーアクションRPGです。崩壊後のニューオーリンズを舞台に、物資の探索やクラフトを行い生き延びる道を模索し、時に道徳的な選択を迫られる、自由度の高いプレイが特徴です。プレイヤーは、限られた弾薬や回復アイテムの管理、死のリスクを伴う探索など、緊張感のあるサバイバル体験を味わうことができ、VRならではの直感的な近接戦闘や没入感も高く評価されています。豊富なアップデートとともに、長く遊べる名作です。
『Identity V(第五人格)』
スマホ向けの非対称対戦型(1対4)のサバイバルホラーゲームで、1人のハンターと4人のサバイバーが、それぞれの目的でスリリングな鬼ごっこを繰り広げます。対戦中は協力や牽制といったリアルタイムの連携が重要になり、友人同士でも楽しめるマルチプレイ対応や、協力プレイの戦略性の高さなどで世界中のプレイヤーに親しまれている、モバイルホラーの定番タイトルです。また、豊富なキャラクターやスキン、他作品とのコラボ展開も好評を博しています。
サバイバルホラーゲームに仕事としてかかわるには?
サバイバルホラーゲームを作るにあたって、必要とされるスキルや専門性は職種によって異なりますが、「恐怖をどう体験させるか」という視点が重要である点は共通しています。今回は、主要な開発職について「プレイヤーに恐怖を体験させるには」という観点からご紹介します。
ゲームプランナー
ゲーム全体の骨組みを考える中心的な役割で、サバイバルホラーでは「プレイヤーがどう恐怖を体験するか」を設計する重要なポジションとなります。アイテムの量や配置、演出の間など、緊張を生む仕掛けをロジカルに組み立てる創造性と、プレイヤー視点で物事をとらえる感覚が不可欠です。この視点を鍛えるには、ホラー映画や実際のゲーム作品を分析し、「なぜ怖いのか」を言語化する習慣を持つとよいでしょう。
▼ゲームプランナーについてはこちらで詳しく紹介しています!

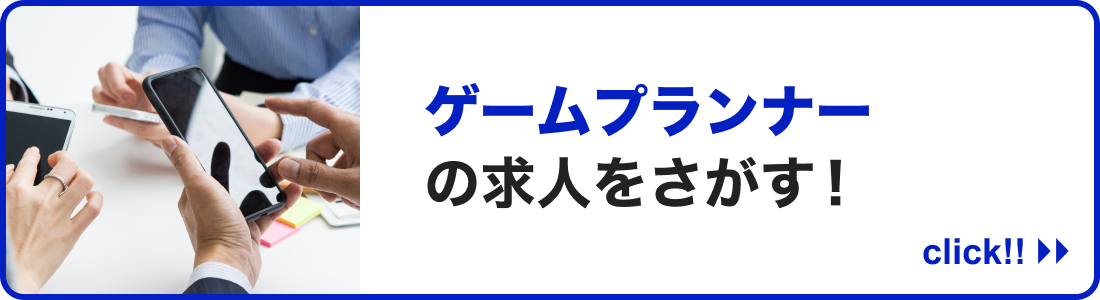
2D・3Dデザイナー
操作感、演出、マップ構造といったゲーム内部の設計を担うポジションです。世界観やUI(操作画面)の設計も含め、「閉鎖空間での孤独感」や「限られた行動範囲」など、サバイバルホラー特有の緊張感を生み出すためのさまざまな仕組みを形にします。小さな演出の積み重ねがプレイヤー体験を大きく左右しますから、怖さを引き出す空間設計や操作感に注目しつつ、他ジャンルのデザインとの違いも比較、研究してみましょう。
▼2D・3Dデザイナーについてはこちらで詳しく紹介しています!


サウンドクリエイター
音によって恐怖を支えるプロフェッショナルです。環境音の静寂や、背後からの足音、セーブ部屋の安心感――音は感情に強く訴えかけますし、BGMや効果音だけだなく、何も鳴らない「無音」もまた重要な演出です。
サバイバルホラーは特に繊細な音作りが求められる分野で、シーンごとの心理効果を考慮するセンスが必要になります。そのため、映像作品やホラーゲームの音による演出を「耳で観る」よう意識して鑑賞してみるのも、おすすめです。
▼サウンドクリエイターについてはこちらで詳しく紹介しています!


制作ツール
サバイバルホラーゲームの制作に使えるツールは、初心者向けから中・上級者向けまで幅広く存在しますので、目的やスキルレベルに応じて、適切なものを選びましょう。ここでは代表的なツールをいくつかご紹介します。
初心者向けサバイバルホラーゲーム制作ツール
RPGツクールシリーズ
手軽に始めたい方におすすめのツールです。プログラミングが苦手でも、GUI操作でほとんど完結できる上、素材が豊富で日本語情報も多いので、初心者の方でも手を出しやすいでしょう。
WORF RPGエディター(ウディタ)
無料で利用可能なゲームエンジンです。RPGツクールと同じくノーコードで制作できますし、公式のマニュアルがかなり詳細で手厚いです。ウディタで制作したゲームは配布・販売・コンテスト投稿などが可能で、有名なフリーホラーゲームの開発にも多用されています。
中・上級者向けサバイバルホラーゲーム制作ツール
Unity
Unityは、幅広い分野で、世界中の開発者に利用されている、定番のゲームエンジンです。2D、3Dの両方に対応していて、アセットストアには本格ホラー用テンプレートや素材が豊富にあり、カスタマイズ性も高いので、3Dサバイバルホラー、FPS、VRなど、様々な本格的なゲーム開発が可能です。
Unreal Engine5
Unreal Engineは高品質な3Dグラフィックと、Blueprintによるノーコード開発が可能なゲームエンジンで、ゲーム以外でも映画や建築など、様々な用途で利用されています。Unreal Engine5では、これまでのバージョンと比較して、グラフィック性能が大幅に強化されました。また、ゾンビAIやインタラクション、エフェクトなどのチュートリアルや講座も充実しており、AIや物理演算の本格実装が可能ですが、PCの推奨スペックは高めなので、導入の際は注意してください。
まとめ
サバイバルホラーゲームは、プレイヤー自身が「どう生き延びるか」を考えながら進めていく、緊張感と没入感に満ちた“体験型”のジャンルです。映画や小説では味わえない、“自分ごと”としての恐怖を体感できる点は、ゲームならではの大きな魅力といえるでしょう。
今では、コンシューマーからスマホアプリ、VR、インディー作品まで、幅広く展開されており、プレイヤーの好みに合った“ちょうどいい怖さ”を選べる時代になっています。ホラーが好きな方はもちろん、少しでも気になる方は、この機会になにか一作品試してみてはいかがでしょうか。
ゲーム・エンタメ業界での転職ならコンフィデンスクリエイター
Confidence Creator(コンフィデンスクリエイター)はゲーム・エンタメ業界に特化した人材事業を展開する株式会社コンフィデンス・インターワークスが提供する総合人材サービスです。
ゲーム・エンタメ業界の大手・上場企業を中心に300社以上の取引実績を持ち、常時月間300件以上の新規案件を保有。 コンフィデンスクリエイターにしかない非公開案件も多数ございます。
これまでゲーム・エンタメ業界で築いてきた信頼関係の強さを活かし、制作現場を熟知したコンサルタントがゲーム・エンタメ業界で働くみなさまのご経歴やご希望、これからのキャリアビジョンに応じて最適なマッチングを行います。
ゲーム・エンタメ業界でのキャリアアップを目指す方も、ご自身のキャリアについて漠然と悩みを持っている方も、まずはお気軽にご相談ください!